文学部文学科フランス文学専修
フランスを知る、国境を超える。ここには〈いま〉への関心が生きています。
専修の特徴
本当のフランスって?
私たちはいろいろな外国に、それぞれ固定したイメージを持ちやすいものです。フランスについても、私たちのまわりにはさまざまなほめ言葉や悪口が溢れていますが、現実のフランスは、どうもそういったイメージとはかけ離れているようです。EU、多文化主義、そして新しい文学や芸術。ここには、きわめて多様な、あふれんばかりのエネルギーがあって、それは今でもとても魅力的です。
現代的なものへの関心
立教大学のフランス文学専修は、何よりもこのアクチュアルなフランスに密着していきたいと願っています。生きている人間が、現代的なものへと最初に眼を向けるのは当然のことでしょう。この関心のなかにこそ、私たち一人ひとりの個性が現われてきます。フランス文学専修が大切な出発点にするのは、私たちの誰もが持っているはずの現代的なものへの、いきいきとした関心なのです。近・現代の社会、思想、文学を専門にする教員がこの専修に多いのも、そのためといえるでしょう。
教養はなぜ必要か
もちろん、立教大学のフランス文学専修には、中世・ルネサンス、あるいは17・18世紀の歴史や文学を教える先生もいます。けれども、教養主義的なものがそこで漠然と目指されているわけではありません。現代的なものへの私たちの切実な関心は、たちまちそうした遠い過去をも自分たちに必要な知恵として引き込み始めるのです。「いま」を知ろうとすればするほど、その「いま」はどんどん遠くに拡がって歴史や古典につながっていくのです。
実践的なフランス語力を身につけるために
外国語の勉強についても同じようなことがいえるでしょう。誰かがある外国語をなかなか身につけることができないとしたら、それはその言葉が、その人にとって本当に必要なものになっていないからです。立教大学のフランス文学専修は、意欲のある学生のためにフランス語の効率的な教授法を工夫することにとても多くの力を注いでいます。全学共通の外国語科目のほかに、多様な関心や必要に応じたフランス語の授業が独自に設けられています。これらの科目はどれも、みなさんの実践的なフランス語力を磨くためのものです。
フランスからあなたの「いま」へ
グローバル化する現代、ヨーロッパの言語や文化を修得することの意味はますます増しています。フランスとの交わりを通して西洋を見、イスラム世界やアジアを考え、そして日本へと戻ってくる。フランス文学専修は、そんなみなさんを支えるところです。
在学生からのメッセージ

文学科フランス文学専修4年次 高杉 芽衣さん 東京都 田園調布学園高等部出身
視野を広げてくれる環境で、研究を深める
ゼミで作品に対する意見交換を行ううちに、自分では気づかなかった視点を得られ、視野が広がりました。活発な議論に触発され、今では自分が最初に発言するように。卒業論文はジュール・シュペルヴィエルという作家の著作に注目して、「変身」というテーマで執筆しています。卒業後は大学院に進学し、在学中に身につけた知識や視点を活かして研究を深めたいと考えています。
今のわたしを作る、この一冊。
短編集ですが、どれも予想外の展開ばかりで読者を退屈させません。思わず笑ってしまう独特な表現がたくさんありますが、悲しい結末のものが多く、心が大きく揺さぶられます。
海に住む少女 ジュール・シュペルヴィエル 著、永田 千奈 訳
光文社古典新訳文庫/2006年10月発行
ゼミで作品に対する意見交換を行ううちに、自分では気づかなかった視点を得られ、視野が広がりました。活発な議論に触発され、今では自分が最初に発言するように。卒業論文はジュール・シュペルヴィエルという作家の著作に注目して、「変身」というテーマで執筆しています。卒業後は大学院に進学し、在学中に身につけた知識や視点を活かして研究を深めたいと考えています。
今のわたしを作る、この一冊。
短編集ですが、どれも予想外の展開ばかりで読者を退屈させません。思わず笑ってしまう独特な表現がたくさんありますが、悲しい結末のものが多く、心が大きく揺さぶられます。
海に住む少女 ジュール・シュペルヴィエル 著、永田 千奈 訳
光文社古典新訳文庫/2006年10月発行
卒業生からのメッセージ

フランス国立東洋言語文化大学 日本学部 教諭 須藤 瑠衣さん 2012年度文学科フランス文学専修卒業
外国文学の世界を深く覗いてみたいという思いから、フランス文学専修を選択しました。在学中に留学を経験し、フランスにおける日本語教育に興味を持つようになりました。現在はパリの大学で日本語を教えています。私自身が大学で学んだように、フランスの学生達に日本という新たな世界への扉を開く、日仏の架け橋のような存在になりたいです。
今のわたしを作る、この一冊。
この作品が、文学が日常に眠る真実を教えてくれることに気づかせてくれました。昼夜を分かたず読み続けたくなる傑作です。
失われた時を求めて マルセル・プルースト 著、吉川 一義 訳
岩波書店/2010年11月発行
今のわたしを作る、この一冊。
この作品が、文学が日常に眠る真実を教えてくれることに気づかせてくれました。昼夜を分かたず読み続けたくなる傑作です。
失われた時を求めて マルセル・プルースト 著、吉川 一義 訳
岩波書店/2010年11月発行
教員からひとこと
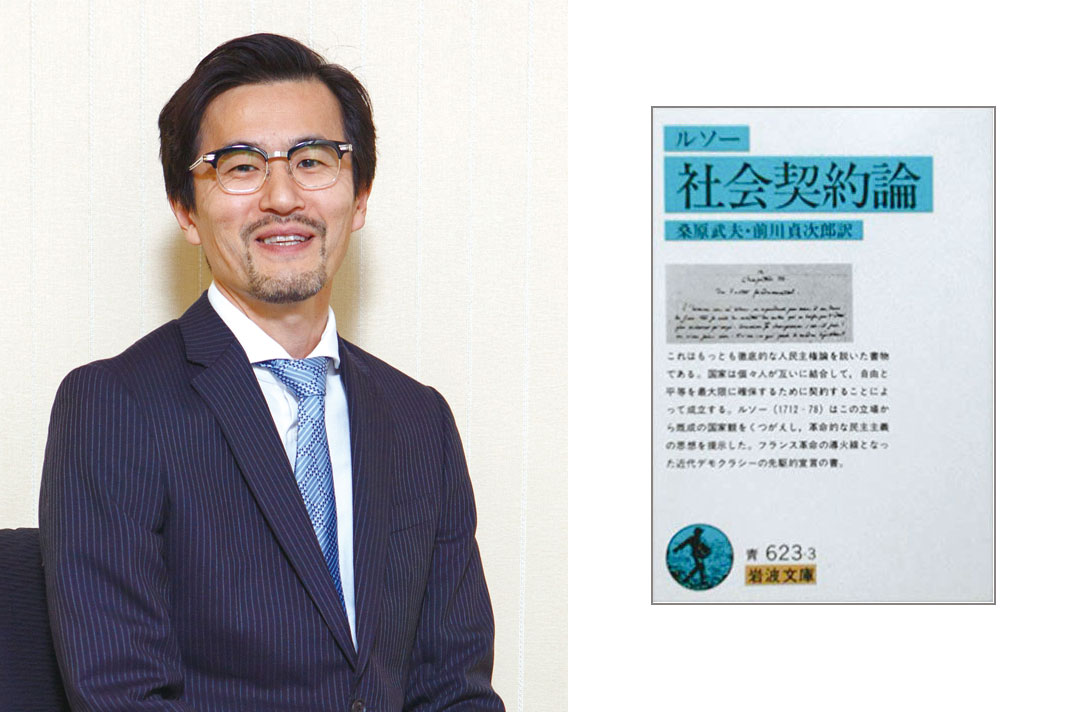
桑瀬 章二郎教授 [研究テーマ:18世紀フランス文学・思想]
本学文学部文学科フランス文学専修があくまで専修というかたちをとっているのは、文学科、さらには文学部の一部であることを常に意識することで、文学と呼ばれる広大な宇宙に開かれていたいと願っているからです。もちろんまずはフランスについて深く学んで欲しいと思いますし、私自身、フランスの文化や歴史、文学や哲学を中心に研究しています。ですが、フランスはあくまで世界への入口にすぎません。どんどん内向きになっているこのご時世、恐れず、「外」へ、果てしなく広がる「向こう」へ出発してみませんか。
今のわたしを作る、この一冊。
私にとってこの作品は、私たちが当たり前だと思っている現在進行形の現象について、根幹から考えるよう、考え直すよう、迫ってくるような「古典」です。
社会契約論 ジャン=ジャック・ルソー 著、桑原 武夫、前川 貞次郎 訳
岩波書店/1954年12月発行
今のわたしを作る、この一冊。
私にとってこの作品は、私たちが当たり前だと思っている現在進行形の現象について、根幹から考えるよう、考え直すよう、迫ってくるような「古典」です。
社会契約論 ジャン=ジャック・ルソー 著、桑原 武夫、前川 貞次郎 訳
岩波書店/1954年12月発行
